第19回 糖尿病の注意点
糖尿病に関する話 ~糖尿病の注意点~
2017.11.28
細菌感染症で重症化 水虫や歯周病も危険
【相談者】
Sさん 50歳男性。病院で糖尿病と診断され、治療を始めることになりました。運動療法、食事療法、薬物療法が治療の基本と言われました。さらに生活面で気を付けたらよいことはありますか。
糖尿病の患者さんは、高血糖の状態が続くとさまざまな細菌やウイルスなどによる病気にかかりやすくなります。また血糖値のコントロールが悪いと重症化しやすく、感染症によって血糖コントロールがさらに悪化する悪循環に陥ります。
糖尿病になるとかかりやすい細菌感染症には、気管支炎、結核、胆のう炎、腸炎、尿路感染症、皮膚感染症などがあります。
皮膚の感染症には細菌に加えて足の指、爪などに水虫(白癬(はくせん))やカンジタなどの真菌による感染症も起こりやすくなります。放置すると、足の組織が死んでしまう「壊疽(えそ)」につながることもあります。
歯周病にも注意が必要です。歯周病は歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)から歯周病菌の感染により歯肉の炎症を起こす病気です。放置すると歯を支えている骨を破壊し歯を失うことにもなります。
冬季に流行しやすいインフルエンザにもかかりやすくなります。特に高齢の患者さんは肺炎など重症化しやすいので注意が必要です。インフルエンザの予防には、うがいや手洗いをすること、流行する前に予防接種を受けることをお勧めします。
■足を守るためには?
糖尿病の人は特に足を守る必要があります。糖尿病神経障害が進行すると足の感覚が鈍くなり、けがをしても気づきにくくなります。動脈硬化で足の血管内が細くなり足の先まで必要な酸素や栄養が届きにくくなります。細菌に対する抵抗力が落ちているため傷の回復が遅れ化膿しやすくなります。こうしたことから、ささいなけがが、壊疽や切断に至ることがあります。
水虫は糖尿病患者さんの約6割以上がかかっているとの報告があります。足の水虫から細菌感染を起こして壊疽になることもあります。たかが水虫と油断しないで皮膚科へ受診し治療することが大切です。
また、寒い時期は暖房器具やカイロなどで低温やけどを起こしやすくなります。特に神経障害があると温度に対する感覚が鈍くなりますので注意が必要です。暖房器具の温度は低めにして、カイロを直接足に貼ったり靴の中に入れたりすることはやめましょう。
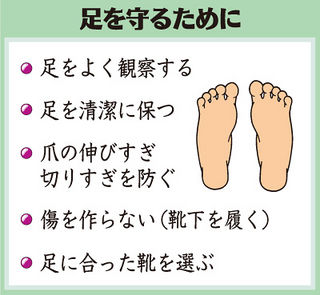
足を守るためには日頃から清潔に保ち、よく観察して、手入れをこまめにすることなどが大切です。そして、異常があれば自己判断せず早めに医師や看護師にご相談ください。
■口の手入れは?
歯周病細菌が出す内毒素はインスリンの働きを悪くします。糖尿病があると歯周病は悪化しやすくなり、悪化した歯周病は血糖コントロールを妨げて糖尿病を悪化させます。歯周病は口腔(こうくう)内だけにとどまらず心筋梗塞、感染性心内膜炎、呼吸器疾患、低体重児出産などの誘因となる可能性も指摘されています。
歯周病の予防は毎日の歯磨き(プラークコントロール)です。歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロスなどを用いて丁寧に口腔ケアを行いましょう。またかかりつけの歯科医をつくり、定期的に受診しましょう。
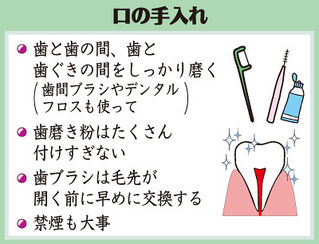
糖尿病患者さんが感染症から重症化しないためには、日頃の血糖コントロールを良好にしておくことがとても重要です。そのためには、食べ過ぎ、飲み過ぎに気を付け、禁煙、血流改善のため適度な運動をしましょう。肥満を予防し、こまめに体重測定をしましょう。
一病息災! 糖尿病とうまく付き合っていきましょう。
【相談者】
Sさん 50歳男性。病院で糖尿病と診断され、治療を始めることになりました。運動療法、食事療法、薬物療法が治療の基本と言われました。さらに生活面で気を付けたらよいことはありますか。
糖尿病の患者さんは、高血糖の状態が続くとさまざまな細菌やウイルスなどによる病気にかかりやすくなります。また血糖値のコントロールが悪いと重症化しやすく、感染症によって血糖コントロールがさらに悪化する悪循環に陥ります。
糖尿病になるとかかりやすい細菌感染症には、気管支炎、結核、胆のう炎、腸炎、尿路感染症、皮膚感染症などがあります。
皮膚の感染症には細菌に加えて足の指、爪などに水虫(白癬(はくせん))やカンジタなどの真菌による感染症も起こりやすくなります。放置すると、足の組織が死んでしまう「壊疽(えそ)」につながることもあります。
歯周病にも注意が必要です。歯周病は歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)から歯周病菌の感染により歯肉の炎症を起こす病気です。放置すると歯を支えている骨を破壊し歯を失うことにもなります。
冬季に流行しやすいインフルエンザにもかかりやすくなります。特に高齢の患者さんは肺炎など重症化しやすいので注意が必要です。インフルエンザの予防には、うがいや手洗いをすること、流行する前に予防接種を受けることをお勧めします。
■足を守るためには?
糖尿病の人は特に足を守る必要があります。糖尿病神経障害が進行すると足の感覚が鈍くなり、けがをしても気づきにくくなります。動脈硬化で足の血管内が細くなり足の先まで必要な酸素や栄養が届きにくくなります。細菌に対する抵抗力が落ちているため傷の回復が遅れ化膿しやすくなります。こうしたことから、ささいなけがが、壊疽や切断に至ることがあります。
水虫は糖尿病患者さんの約6割以上がかかっているとの報告があります。足の水虫から細菌感染を起こして壊疽になることもあります。たかが水虫と油断しないで皮膚科へ受診し治療することが大切です。
また、寒い時期は暖房器具やカイロなどで低温やけどを起こしやすくなります。特に神経障害があると温度に対する感覚が鈍くなりますので注意が必要です。暖房器具の温度は低めにして、カイロを直接足に貼ったり靴の中に入れたりすることはやめましょう。
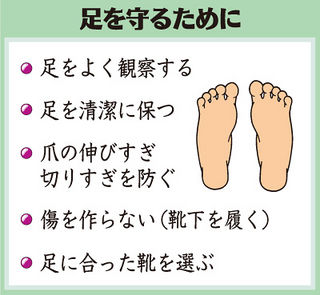
足を守るためには日頃から清潔に保ち、よく観察して、手入れをこまめにすることなどが大切です。そして、異常があれば自己判断せず早めに医師や看護師にご相談ください。
■口の手入れは?
歯周病細菌が出す内毒素はインスリンの働きを悪くします。糖尿病があると歯周病は悪化しやすくなり、悪化した歯周病は血糖コントロールを妨げて糖尿病を悪化させます。歯周病は口腔(こうくう)内だけにとどまらず心筋梗塞、感染性心内膜炎、呼吸器疾患、低体重児出産などの誘因となる可能性も指摘されています。
歯周病の予防は毎日の歯磨き(プラークコントロール)です。歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロスなどを用いて丁寧に口腔ケアを行いましょう。またかかりつけの歯科医をつくり、定期的に受診しましょう。
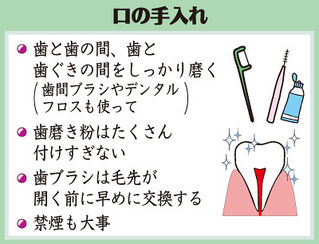
糖尿病患者さんが感染症から重症化しないためには、日頃の血糖コントロールを良好にしておくことがとても重要です。そのためには、食べ過ぎ、飲み過ぎに気を付け、禁煙、血流改善のため適度な運動をしましょう。肥満を予防し、こまめに体重測定をしましょう。
一病息災! 糖尿病とうまく付き合っていきましょう。