検体検査
① 血液検体検査
採血について
生化学検査
血清検査
血液検査
輸血関連検査
② 一般検査
尿検査
便潜血反応
③細菌検査
提出された検査材料(喀痰・咽頭粘液・血液・膿・便など)を寒天培地に塗り、ふ卵器で培養し、細菌を発させます。そして菌名を明らかにして、どの薬が治療に有効か調べます。
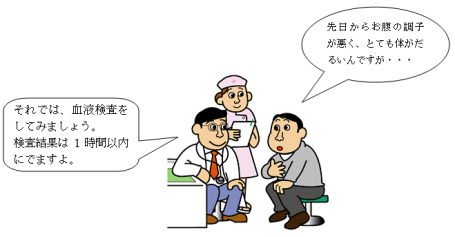
検査項目と基準値
1. 主に肝臓・胆のうの機能を知るための検査
GOT(AST)
基準値 : 12-31 U/l
分かること : 肝臓や心臓などの細胞中に含まれる酵素。肝臓や心臓などが障害された際に、血液中に漏れ増加する。
GPT(ALT)
基準値 : 8-40 U/l
分かること : 肝臓や腎臓、心臓などの細胞中に含まれる酵素。肝臓などが障害された際に、血液中に漏れて増加する。GPTはGOTに比べて肝障害に特異性が高い。
LDH
基準値 : 110-210 U/l
分かること : あるゆる臓器に広く分布し、LDHが増加するのは、いずれかの臓器で細胞が破壊され、血液中に漏れ出しいることを意味し、スクリーニングに位置づけられる酵素。急性肝炎、心筋梗塞などが疑われる。また、悪性腫瘍、血液疾患で上昇する。
ALP
基準値 : 100-330 U/l
分かること : 肝臓、骨、胎盤、小腸に由来しており、主な検査目的としては、肝・胆道疾患、特に胆汁流出障害の有無、骨疾患で上昇することがある。
γ-GTP
基準値 : 男 11-73 U/l、女 9-49 U/l
分かること : 主に肝・胆道系の疾患を特異的に反映する。アルコール性肝障害発見の手がかりとなる。
CH-E、コリンエステラーゼ
基準値 : 200-459 U/l、0.54-1.30 δpH
分かること : 肝細胞で生産され、肝実質障害により低下し、経過の改善に伴って上昇し基準値に復する。値が低い場合は肝硬変、肝臓癌などが、高い場合は脂肪肝、ネフローゼなどが疑われる。アルブミン量と平行し、肝内蛋白合成能の指標となる。
T-Bil 総ビリルビン、D-Bil 直接ビリルビン
基準値 : 0.2-1.2 mg/dl、0.0-0.4 mg/dl
分かること : 肝機能検査の中ではきわめて重要なものであり、各種肝・胆道疾患の診断、経過観察、予後判定や黄疸の鑑別に用いられる。
TTT
基準値 : 1.3-7.8 U
分かること : 血清に試薬を加え、混濁の程度で肝臓の状態を判別する。
ZTT
基準値 : 3.4-13.4 U
分かること : 血清に試薬を加え、混濁の程度で肝臓の状態を判別する。免疫グロブリンと相関し、慢性肝炎・膠原病などで上昇する。
TP 総蛋白
基準値 : 6.7-8.3 g/dl
分かること : 血清中の蛋白質の総量で、約60%のアルブミンと20%のγグロブリンが大部分を占める。肝機能や腎機能の障害などの異常を調べる。
ALB アルブミン
基準値 : 3.8-5.3 g/dl
分かること : 肝臓で合成される血清総蛋白の約60%を占める成分である。全身栄養状態、肝機能障害、ネフローゼの検査として利用される。
A/G
基準値 : 1.5-2.3
分かること : アルブミンとγ-グロブリンの割合。肝機能等に異常が生じると値が低くなる。
2. 糖尿病など主にすい臓の機能を知るための検査
Glu血糖
基準値 : 70-109 mg/dl
分かること : 血液中のグルコースのことをいい、空腹時の血糖値は恒常的に調整されている。血糖調整の最大の因子はすい臓のインスリンであり、不足すると高血糖になり、過剰では低血糖になる。
HbA1C グリコヘモグロビン A1C (NGSP)
基準値 : 4.6-6.2 %
分かること : 過去1~3ヶ月間の血糖値を反映する。長期間の血糖コントロールの指標となり、糖尿病の検査として重要。
S-AMY アミラーゼ
基準値 : 30-116 U/l
分かること : アミラーゼのほとんどはすい臓と唾液腺由来のものである。すい臓の障害により、血液中に漏れ増加する。すい臓病のスクリーニング、早期診断に役立つ。
3. 主に高脂血症・高血圧・動脈硬化・心臓病などに関する検査
T-CH 総コレステロール
基準値 : 150-220 mg/dl
分かること : 食物からの摂取、肝臓での生合成その他にて保たれている。肝臓の状態、脂質代謝異常の解明や動脈硬化の危険性の予知にも有用である。
HDL-C
HDL コレステロール
基準値 : 41-95 mg/dl
分かること : 血管に付着したコレステロールを運び去り、動脈硬化を予防してくれる。喫煙や炭水化物の取りすぎ等で低下し、運動や低脂肪食で上昇する。「善玉コレステロール」と呼ばれている。
LDL-C
LDLコレステロール
基準値 : 70-139 mg/dl
分かること : LDL-Cが増えると、体の隅々に運ばれるコレステロールが増えて動脈硬化を促進する方向に働く。「悪玉コレステロール」と呼ばれている。
TG 中性脂肪
基準値 : 30-150 mg/dl
分かること : 増加すると、肥満や脂肪肝、動脈硬化の原因になる。また、HDLコレステロールを下げる原因ともなる。
CK
基準値 : 男 65-275 U/l、女 50-170 U/l
分かること : 心筋、骨格筋に存在する酵素で、細胞の損傷によって血液中に出る酵素である。心筋梗塞で上昇し、激しい運動にても上昇する。
4. 主に腎臓の機能を知るための検査
UA 尿酸
基準値 : 男 3.2-7.7 mg/dl、女 2.7-5.8 mg/dl
分かること : 高尿酸血症は体内における生成亢進(痛風等)や腎臓からの排泄異常に起因する。
BUN 尿素窒素
基準値 : 8.0-22.0 mg/dl
分かること : 血中の尿素に含まれる窒素分を表す。肝臓で合成され、尿中に排泄される。腎臓での排泄機能に異常が生じると高値になる。
CRE クレアチニン
基準値 : 男 0.60-1.10mg/dl、女 0.40-0.80mg/dl
分かること : 腎臓の機能が低下すると排泄できなくなり、血液中に増加する。
eGFR
基準値 : 90以上
分かること : 年齢・血清クレアチニン値・性別を用いて、腎臓の働きを算出する。生活習慣病に関する全ての疾患は、慢性腎臓病と関係があり、腎臓病の「早期発見と早期治療」に役立つ。
5. 主に水分・電解質代謝を知るための検査
Na ナトリウム、Cl クロール
基準値 : 138.0-146.0 mEq/l、99.0-109.0 mEq/l
分かること : NaとClはNaClとして大部分細胞外液中に存在し、他の電解質との相互関係のもとに水分・浸透圧の調整などに重要な役割をしている。
K カリウム
基準値 : 3.60-4.90 mEq/l
分かること : Kは細胞内に存在する。腎臓からの排泄と細胞内外の分布を調整することにより維持される。濃度の異常は神経・心筋などに機能障害を引き起こす。
Ca カルシウム
基準値 : 8.5-10.4 mg/dl
分かること : 成人の生体には約1KgのCaが存在するが、99%は硬組織(骨)に含まれ、1%が軟部組織などに存在する。血液中に存在するCaは約0.1%にすぎない。酵素の活性化、血液凝固、筋収縮、神経刺激伝導に必須である。主に副甲状腺ホルモンとビタミンDにより調整されている。したがって、ホルモン異常や骨、腎臓の異常により、Ca値に異常をきたす。
P 無機リン
基準値 : 2.5-4.5 mg/dl
分かること : Pは糖質代謝、エネルギー代謝に必須の物質である。体内総Pの80-85%は骨でCaと結合している。Pも副甲状腺ホルモンにより調整されている。したがって、Ca,ALPの変動と関連して検査することにより、病態を把握できる。
6. 貧血など主に血液の異常を知るための検査
WBC 白血球数
基準値 : 男 3.5-9.0 ×103/μl、女 3.5-8.5 ×103/μl
分かること : 正常よりも増加している白血球増加症は、種々の感染症の際に起こる。白血球減少症は、放射線照射や薬物投与などにより骨髄の造血機能が障害された際に起こる。
RBC 赤血球数
基準値 : 男 4.20-5.60×106/μl、女 3.80-5.00×106/μl
分かること : 血液中の赤血球数を調べる検査。血色素量、ヘマトクリットとともに貧血等の状態を調べる。
Hb 血色素量
基準値 : 男 13.5-17.5 g/dl、女 11.5-15.0 g/dl
分かること : 酸素を運ぶ赤血球中の蛋白の一種で、減少すると貧血が疑われる。
Ht ヘマトクリット
基準値 : 男 41.0-52.0%、女 34.0-45.0 %
分かること : 血液中に含まれる赤血球の容積の割合を調べる。減少すると貧血が疑われる。
PLT 血小板数
基準値 : 男 150-360×103/μl、女 140-350×103/μl
分かること : 血小板は出血を止める働きをする。骨髄機能が衰退した場合には白血球数とともに減少する。また、減りすぎた場合には貧血や白血病等も疑われる。
CRP
基準値 : 0.0-0.3 mg/dl
分かること : 炎症性疾患で鋭敏に上昇し、病態の改善後速やかに低下する。病態の診断、予後の判定、治療効果の観察に役立つ。肺炎などの細菌感染症では著しく上昇、悪性腫瘍、膠原病でも活動性の亢進時に上昇する。
FE 血清鉄
基準値 : 男 57-160 μg/dl、女 33-174 μg/dl
分かること : 体内鉄は2/3が赤血球内のヘモグロビンとして、1/3弱が貯蔵鉄として肝臓や骨髄その他の組織に存在する。したがって、造血器の機能を反映し、各種貧血の診断に有用である。